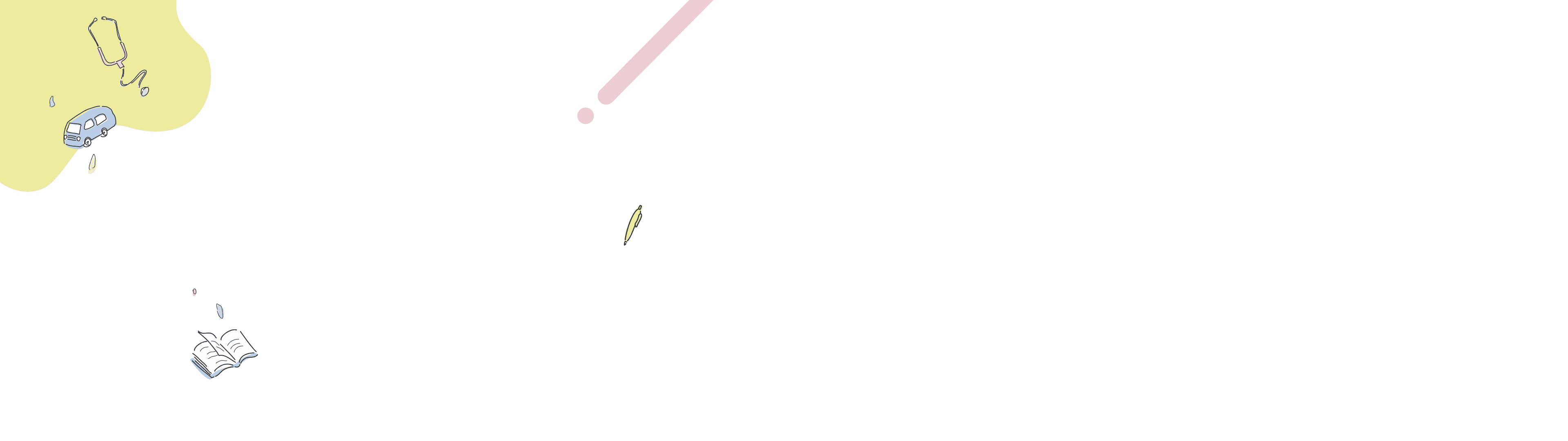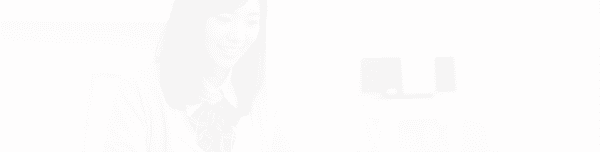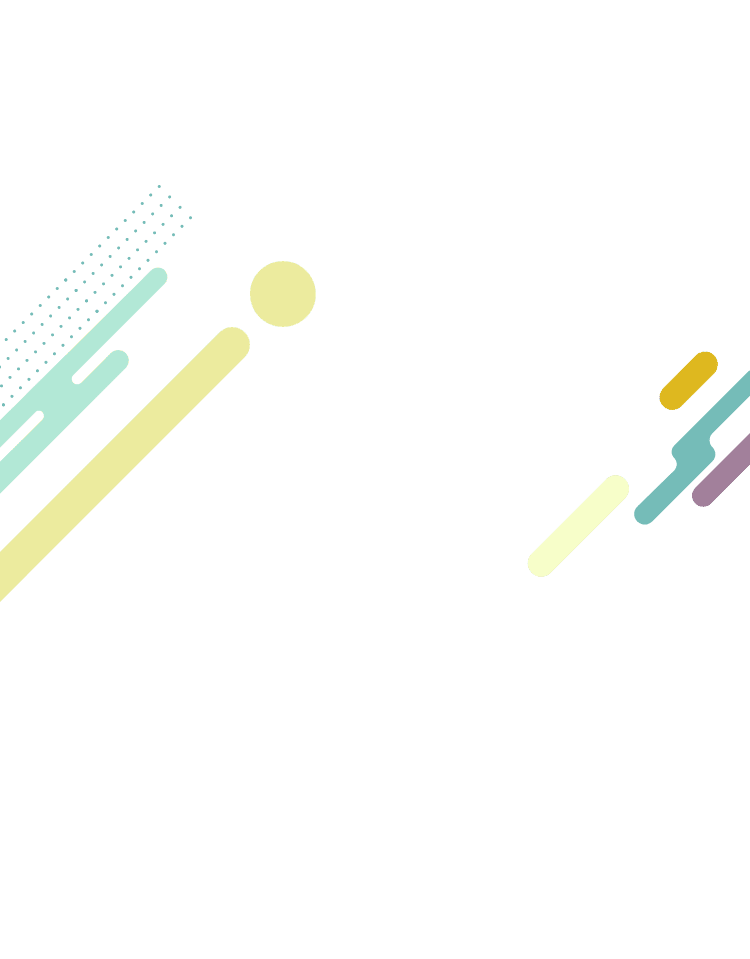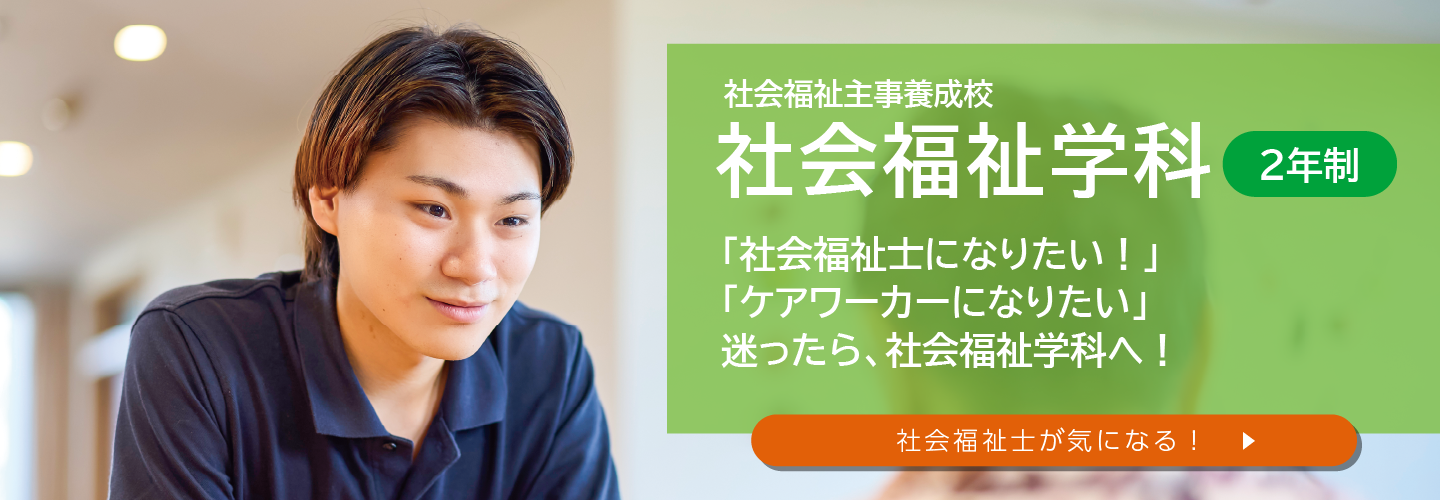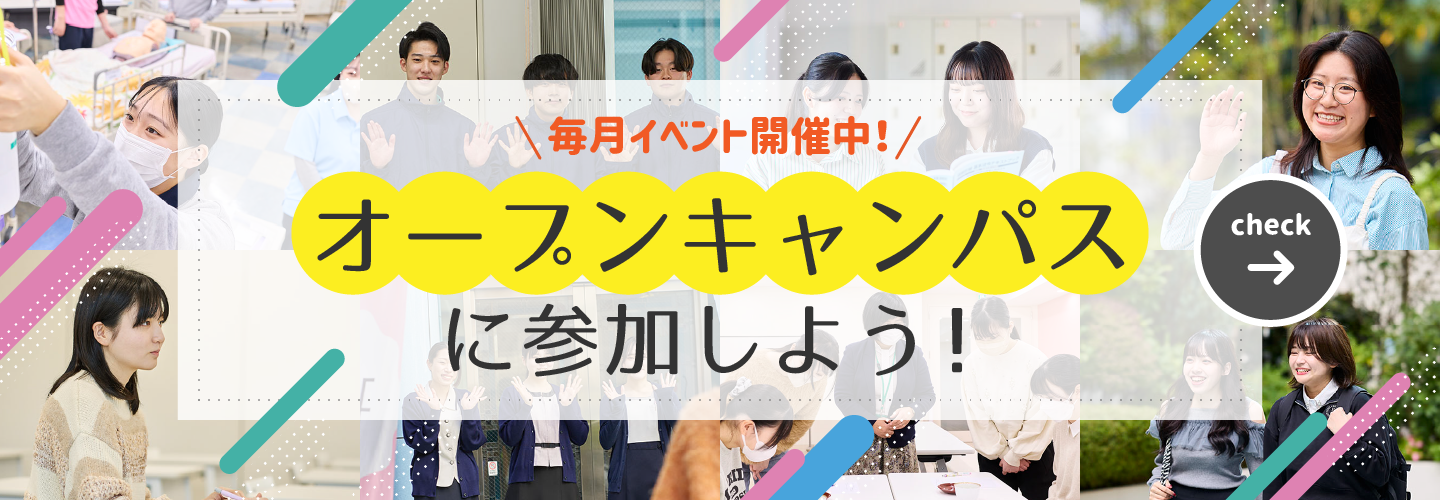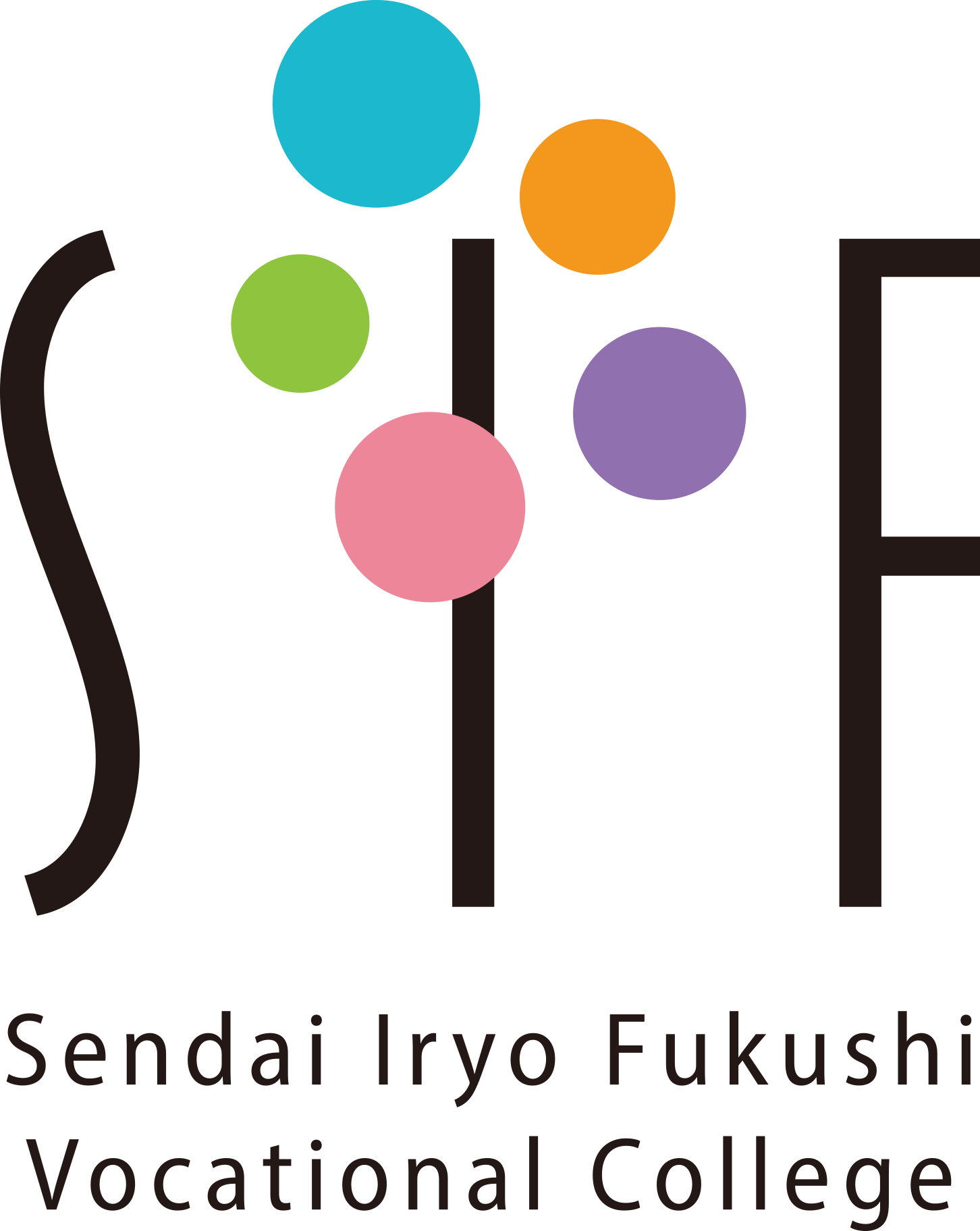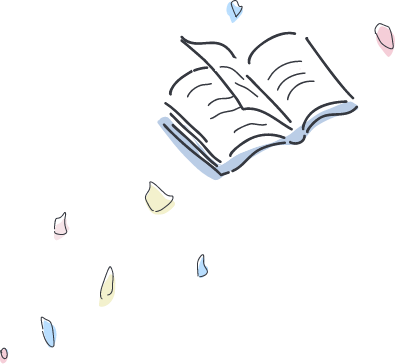
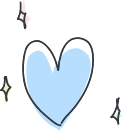
ブログ
BLOG
社会福祉学科
社会福祉士になるなら専門学校と大学どっちがいい?徹底比較します!
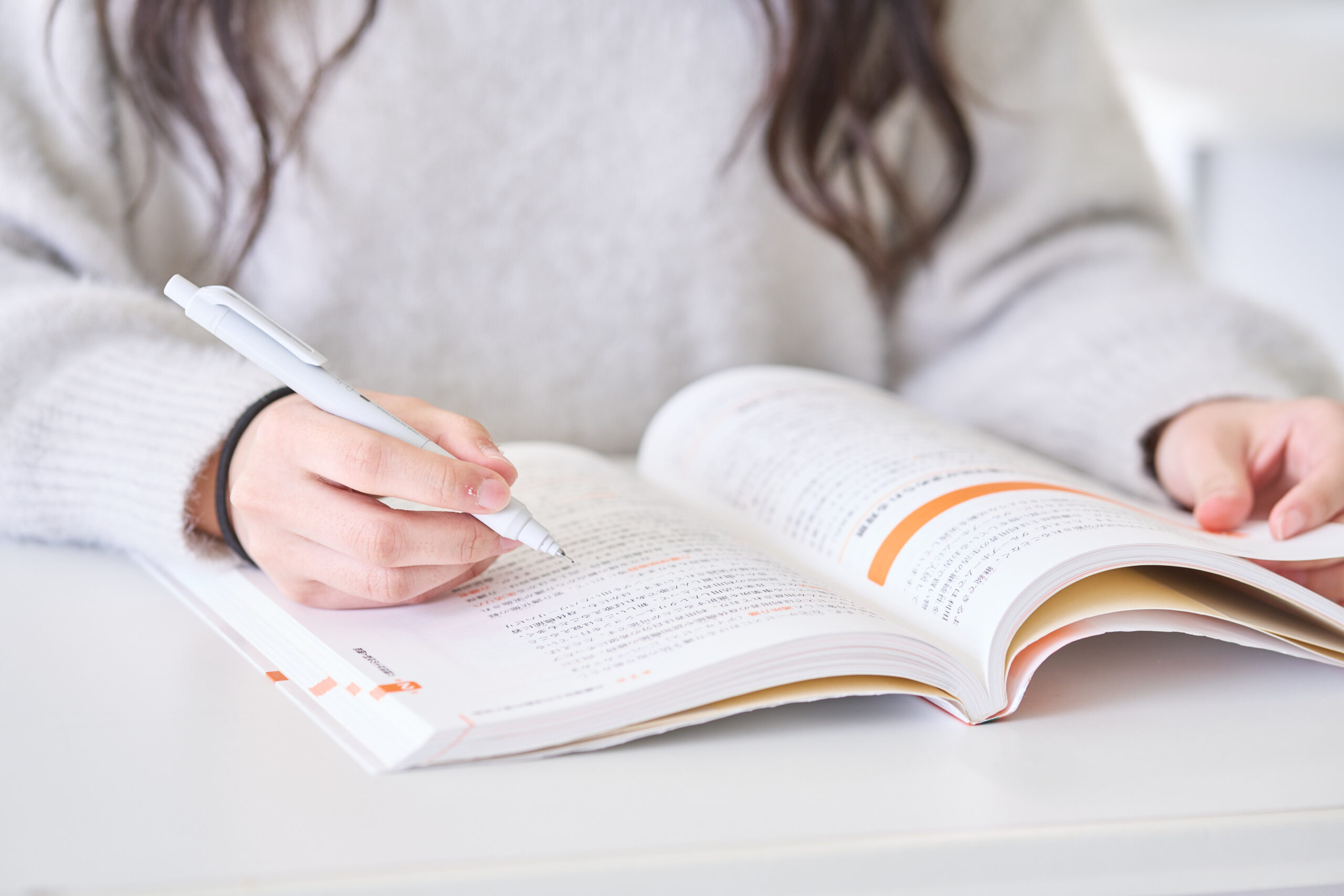
「社会福祉士を目指すなら専門学校と大学どちらがいいんだろう?」
進路選択に悩むみなさんが抱えるこの疑問は、将来の福祉キャリアを左右する重要な問いです。特に高校生の皆さんにとって、この決断は人生の大きな分岐点となります。
この記事では、社会福祉士を目指す際の専門学校と大学の違いを、教育内容から将来性まで医療福祉の専門的視点から徹底比較します。進学に必要な費用、学習環境の違い、国家試験の合格率、将来のキャリアパスまで、客観的なデータと実例をもとに解説します。
進路指導の先生や親御さんからは『大学進学が良い』と言われるかもしれませんが、社会福祉士を目指す道のりは一つではありません。重要なのは、あなた自身の価値観、学習スタイル、そして『どのようなになりたいか』という明確なビジョンに基づいて選択することです
この記事のポイント
- 社会福祉士養成課程における専門学校と大学の7つの本質的な違い
- 教育内容、学習環境、習得スキルの具体的な比較
- 2025年最新の国家試験合格率データと分析
- 将来のキャリアパスと収入見通しの現実的検証
- 本当の適性を知るための自己診断チェックリスト
- 仙台医療福祉専門学校の具体的な教育内容と強み
目次
専門学校と大学の基本的な違い

社会福祉士を目指す上で、専門学校と大学には学習環境から教育内容まで多くの違いがあります。まずは基本的な違いを詳しく見ていきましょう。
学習期間と取得できる学位の違い
専門学校と大学では、学習期間と取得できる称号・学位に大きな違いがあります。
専門学校の場合
- 標準修業年限は2年間
- 卒業時に「専門士」の称号が授与される
- 社会福祉士の受験資格を得るためには、卒業後2年の相談援助実務経験※が必要
- 集中的に専門知識・技術を学ぶカリキュラム構成
大学の場合
- 標準修業年限は4年間
- 卒業時に「学士(社会福祉学)」の学位が授与される
- 幅広い教養科目と専門科目の両方を学ぶ
- 研究的視点を含めた福祉の学びが特徴
「いち早く現場で経験を積みたい」「効率よく専門性を身につけたい」という方には専門学校の2年間という期間は魅力的でしょう。一方、「幅広い教養も含めてじっくり学びたい」「学生生活も大切にしたい」という方には大学が適しているかもしれません。
※厚生労働省の定める相談援助業務(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2に規定)に従事する必要があります。
学費と総費用の比較
進学先を選ぶうえで避けて通れないのが費用の問題です。専門学校と大学では必要な総費用に大きな差があります。
専門学校の費用(概算)
- 2年間の総額:約150万円〜250万円
- 内訳:入学金:10万円〜30万円/年間授業料:70万円〜110万円/実習費・教材費等:10万円〜30万円
大学の費用(概算)
- 4年間の総額:国公立大学:約240万円〜300万円/私立大学:約400万円〜500万円以上
- 内訳(私立大学の場合):入学金:20万円〜30万円/年間授業料:80万円〜120万円/施設設備費等:10万円〜30万円/年
※文部科学省「令和4年度私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」および各種専門学校の公開情報(2024年度)に基づく概算
専門学校は大学に比べて総費用を抑えられる点が大きなメリットです。特に「経済的な負担を減らしたい」「学費の負担を考慮して早く自立したい」と考える方にとっては、専門学校が現実的な選択肢となるでしょう。
日本学生支援機構の給付型奨学金、国の教育ローン、各都道府県の貸付制度、専門学校独自の学費減免制度など、経済状況に応じた支援策があります。詳細は各機関の公式サイトで最新情報をご確認ください
カリキュラムと学びの内容の違い
社会福祉士を目指す専門学校と大学では、学びの内容や深さに大きな違いがあります。
専門学校のカリキュラム特性
- 実践的なスキル習得を中心とした効率的なカリキュラム
- 手話、経済学、法律など福祉の実務を多角的に学ぶ
- 現場経験豊富な教員による実務直結型の指導
- 少人数制による個別最適化された学習環境
- 早期からの体験学習や学外実習による現場感覚の養成
大学のカリキュラム特性
- 社会福祉の理論的基盤と歴史的背景の体系的理解
- 福祉に加えて関連分野や語学、一般教養などの幅広い学び
- 批判的思考力と研究的視点の養成
- ゼミナール活動による専門分野の深化
- 国際的視点と政策的視点を含む包括的な福祉理解
専門学校では「即戦力」を養うことに重点が置かれています。社会福祉士として必要な知識とスキルを効率よく身につけ、現場での実践力を高めることを目指しています。
一方、大学では福祉の本質や背景にある社会構造まで深く理解することに力を入れています。「なぜ」という問いを大切にした学びが特徴で、将来的に福祉政策や研究に関わりたい方に適した環境です。
実習の違いについて
社会福祉士になるためには実習が必須ですが、専門学校と大学では実習の位置づけや進め方にも違いがあります。
専門学校の実習アプローチ
- 早い段階から段階的な実習が始まることが多い
- 現場適応力の早期養成を重視
- 実習と座学の密接な連動による実践的理解の促進
- 実習先施設との緊密な連携体制
大学の実習アプローチ
- 理論的基盤形成後(3〜4年次)の本格的実習
- 事前・事後学習の充実による実習効果の最大化
- 実習体験の理論的分析と振り返りの重視
- 多様な実習先選択と幅広い実践モデルへの接触
どちらの実習も社会福祉士になるために必要な時間数(2023年のカリキュラム改正以降は24日間、180時間以上)は確保されていますが、実習の位置づけや実施時期、学習効果に違いがあります。専門学校では現場感覚を早くから養う一方、大学では理論と実践を結びつける学びが重視されています。
専門学校を選ぶメリット・デメリット

社会福祉士を目指す際、専門学校を選ぶことにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。実際の学生の声も交えながら詳しく解説します。
専門学校のメリット
- 短期間で効率的に資格取得が可能→専門学校では、2年の学習と卒業後2年の相談援助実務経験で社会福祉士の受験資格が得られます。早く現場で活躍したい、早く経済的に自立したいという方にとって、この時間的メリットは非常に大きいでしょう。
- 総費用が比較的抑えられる→大学の4年間と比べると、専門学校の2年間は総費用が約半分で済むケースが多いです。奨学金の返済額も少なく済むため、経済的な負担が少ないのは大きな魅力です。
- 実践的な学びが中心→専門学校のカリキュラムは現場で役立つスキル習得に重点を置いています。実際の福祉現場で使われる技術や知識を効率よく学べるため、即戦力として評価されやすいでしょう。
- 少人数制できめ細かい指導→多くの専門学校では少人数制を採用しており、教員との距離が近いのが特徴です。疑問点をすぐに解消できたり、個別指導を受けたりしやすい環境は、学習効率を高める大きな利点です。
- 就職サポートが手厚い→専門学校は就職実績を重視する傾向があり、就職サポート体制が充実しています。実習先との連携も強く、実習がそのまま就職につながるケースも少なくありません。
「親の経済的負担を少しでも減らしたいと思い、専門学校を選びました。2年間で集中して学び、今は児童養護施設で働いています。学習期間は短かったですが、必要な知識はしっかり身につきましたし、現場での学びも多かったです。」(24歳・専門学校卒業生・児童指導員)
専門学校のデメリット
- 学びの幅が限定的→専門学校では社会福祉士の試験科目を中心に学ぶため、幅広い教養や深い理論的学習の機会は大学に比べると限られています。
- 「大卒」の学歴が得られない→日本社会ではまだ「大卒」という学歴が重視される場面があります。特に一般企業への転職や、将来的な管理職登用の際に不利になる場合もあります。
- 学生生活の経験が限られる→学習時間の限られた専門学校では、大学生活特有の経験(サークル活動、留学、多様な学生との交流など)の機会が少ないのは事実です。人間関係の幅や社会性を広げる経験が限定的になる面も考慮すべきでしょう。
- 研究的視点の養成が少ない→大学で重視される「なぜそうなのか」という研究的視点や批判的思考力の養成は、専門学校では比較的少ない傾向にあります。
- キャリアアップに一定の制約が生じる場合も→大学院進学を希望する場合、専門学校卒では直接進学できず、別途の手続きが必要になることがあります。また、一部の職種では応募資格に「大卒以上」と明記されているケースもあります。
「専門的な知識はしっかり身についたけれど、もう少し福祉の背景にある社会問題や制度の成り立ちについて深く学びたかったなと感じることがあります。今も独学で勉強を続けています。」(26歳・専門学校卒業生・福祉施設相談員)
実際の専門学校の学生の声
専門学校で社会福祉士を目指している学生たちや卒業生の、生の声を紹介します。
「高校生の頃は、ずっと大学進学も考えていましたが、福祉現場で活用できる資格をさまざま取得できることにメリットを感じたので専門学校にしました。今では正解だったと思います。クラスが少人数なので、みんなと深い絆が生まれましたし、先生方も本当に親身になってくれます。資格をきちんと取得して、早く現場で働きたいです。」(専門学校2年生・女性)
「授業や実習が思った以上に充実していて驚きました。1年生から現場を知る機会があり、実際の利用者さんと関わる中で、教科書だけでは学べないことをたくさん学んでいます。先生方も現場経験が豊富で、授業の中でリアルな話を聞けるのが魅力です。」(専門学校1年生・男性)
「専門学校で2年学んだあと、相談援助実務を経験して社会福祉士を目指していました。先生方が卒業生向けに勉強会を開催してくれて、勉強の不安にアドバイスをいただきましたし、ほかの卒業生から刺激を得ることができて良かったです。仕事をしながらの学習は効率が非常に大切で、大変な場面もありましたが、無事に国家試験に合格することができて良かったです。」(専門学校卒業生・男性)
これらの声からもわかるように、専門学校では実践的な学びと手厚いサポートを受けながら、効率よく資格取得を目指せる環境が整っています。
大学を選ぶメリット・デメリット
社会福祉士を目指す際、大学を選ぶことにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。こちらも実際の学生の声を交えながら詳しく解説します。
大学のメリット
- 幅広い教養と深い専門知識→学では社会福祉の専門科目だけでなく、語学、心理学、社会学、法学など幅広い分野の教養を身につけることができます。福祉の背景にある社会構造や人間の本質についての理解を深められるのは大きな魅力です。
- 「大卒」の学歴が得られる→日本社会ではまだ「大卒」という学歴が評価される場面が多いのは事実です。特に一般企業への就職や転職、将来的な管理職登用の際に有利に働くことがあります。
- 多様な学生生活の経験→大学生活ならではの経験(サークル活動、留学、ボランティア、アルバイトなど)を通じて、多様な価値観に触れる機会が豊富です。この経験は社会人になってからも大きな財産になるでしょう。
- 研究的視点が身につく→大学では「なぜそうなのか」という問いを大切にする研究的視点や批判的思考力が養われます。福祉現場の課題を分析し、新たな解決策を考える力は将来的に大きな強みになります。
- キャリアの選択肢が広がる→大学卒業後は、福祉分野だけでなく一般企業への就職、大学院進学、公務員試験など、進路の選択肢が広いのも魅力です。また、福祉分野でもより専門性の高いポジションを目指しやすくなります。
「大学では福祉だけでなく、英語や第二言語、心理学や社会学など様々な学問に触れることができました。この幅広い知識が、現場で利用者さんの多様な問題を理解する力になっていると実感しています。」(28歳・大学卒業生・医療ソーシャルワーカー)
大学のデメリット
- 時間とコストがかかる→大学には4年間通う必要があり、その間の学費や生活費を考えると、総費用は専門学校の約2倍になることもあります。
- 実践的スキルの習得に時間がかかる→大学では理論的な学習が中心のため、現場で即戦力となるような実践的スキルの習得には、専門学校より時間がかかる場合があります。
- 就職までの期間が長い→専門学校なら2年で就職できるところ、大学では4年かかるため、社会人としての収入開始が2年遅れる計算になります。この2年間の機会コストも考慮する必要があるでしょう。
- 資格取得が唯一の目的ではない→大学の社会福祉学部・学科は、社会福祉士資格の取得だけを目的としているわけではありません。そのため、試験対策に特化したカリキュラムではない場合もあります。
- 学習環境が個人の自主性に依存する面がある→大学では自主的な活動が求められることが多く、自己管理能力が試される環境です。自分から積極的に動こうとしない限り、十分な知識やスキルを身につけられない可能性もあります。また、実習や就職活動についても自主的に活動することを求められる傾向にあります。
「大学で学んだことに後悔はありませんが、学費と生活費で奨学金を300万円以上借りることになりました。今後の返済を考えると少し不安ですね。」(26歳・大学卒業生・障害者支援施設職員)
実際の大学生の声
大学で社会福祉士を目指している学生たちの生の声を紹介します。
「社会福祉を学ぶ中で、哲学や心理学、法学など、様々な分野の知識に触れられるのが大学の魅力だと思います。最初は遠回りに感じた教養科目も、今では福祉を多角的に見る視点を養ってくれました。」(大学3年生・女性)
「大学ではサークル活動やボランティア、短期留学など、授業以外にも多くの経験ができます。これらの経験が、将来福祉の現場で多様な人と関わる際の糧になると感じています。」(大学2年生・男性)
「大学では自分で学ぶ姿勢が求められます。誰かに言われなくても自分から調べ、考え、発信する力が身につくのは大きな成長だと思います。ただ、就職活動や国家試験対策は自分でプランを立てる必要があり、その点は大変です。」(大学4年生・女性)
大学生活では、幅広い学びと多様な経験を通じて、福祉専門職としての基盤となる力を培うことができます。自主性を発揮できる環境は、将来的なキャリア形成にも良い影響を与えるでしょう。
社会福祉士国家試験|2025年最新の合格率データと分析
社会福祉士を目指す上で最も気になるのが、国家試験の合格率です。専門学校と大学のどちらを選ぶかを判断する重要な指標として、最新のデータを詳しく分析してみましょう。
全体的な合格率の推移
第36回社会福祉士国家試験(2024年2月実施)の全体合格率は58.1%でした。これは前年の44.2%から大幅に上昇しており、近年では比較的高い合格率となっています。
過去5年間の合格率推移
- 2024年(第36回):58.1%
- 2023年(第35回):44.2%
- 2022年(第34回):31.1%
- 2021年(第33回):29.3%
- 2020年(第32回):29.3%
養成施設別合格率の比較
大学(新卒)の合格率
大学で社会福祉を学んだ新卒者の合格率は65.2%と、全体平均を上回る結果となっています。
専門学校(新卒)の合格率
専門学校で社会福祉を学んだ新卒者の合格率は62.8%で、大学新卒者との差は2.4ポイントとなっています。
実務経験ルートの合格率
専門学校卒業後に2年間の実務経験を積んで受験する場合の合格率は約45%となっており、新卒者と比較すると低い傾向にあります。これは、働きながら勉強することの難しさを反映していると考えられます。
データから読み取れる傾向
1. 新卒時の合格率差は小さい
専門学校と大学の新卒時の合格率差は約2〜3ポイント程度で、統計的には大きな差とは言えません。これは、どちらの教育機関でも適切な試験対策が行われていることを示しています。
2. 実務経験ルートの課題
専門学校卒業後の実務経験ルートでは、仕事と勉強の両立が合格率に影響していると考えられます。ただし、現場経験を積んだ後の受験には、実践的な理解という強みもあります。
3. 個人の学習姿勢が最重要
合格率の差よりも、個人の学習への取り組み方や試験対策の充実度が合格を左右する要因として大きいことがデータから読み取れます。
将来のキャリアパスと収入の違い

社会福祉士として働く際、専門学校と大学のどちらを卒業したかによって、キャリアパスや収入に違いは生じるのでしょうか。長期的な視点で詳しく分析します。
初任給と長期的な収入の比較
初任給の比較: 社会福祉士として就職する際の初任給は、卒業した学校よりも就職先の種別(公務員・社会福祉法人・医療法人など)による差の方が大きいのが実情です。ただし、大卒と専門学校卒では初任給に若干の差がある場合があります。
| 就職先 | 専門学校卒の平均初任給 | 大学卒の平均初任給 |
| 社会福祉法人 | 約18万円〜20万円 | 約19万円〜21万円 |
| 医療機関 | 約19万円〜22万円 | 約20万円〜23万円 |
| 公務員(福祉職) | 約20万円〜23万円 | 約21万円〜24万円 |
| 一般企業(福祉部門) | 約19万円〜21万円 | 約20万円〜23万円 |
長期的な収入の違い: 入職時の差は比較的小さいものの、長期的なキャリアパスでは違いが生じる傾向があります。
- 専門学校卒の場合:現場での実践力を評価され、直接支援の専門職としてのキャリアを積むケースが多
- 大学卒の場合:組織内でのキャリアアップや管理職への道が開かれやすい傾向がある
社会福祉士の給与に関する調査では、勤務先や役職によって収入に差が見られる傾向があります。ただし、個人の能力や努力、取得資格、勤務地域によって大きく変動するため、学歴のみで収入が決まるものではありません。
「専門学校卒業後も学びを継続し、現場経験を積みながら認定社会福祉士の資格を取得しました。実践力と専門性を評価されて、現在は施設のフロア責任者を任されています。学歴よりも実力で評価される職場環境も増えてきていると感じます。」(専門学校卒・福祉施設勤務・32歳)
職場での役割と昇進の違い
社会福祉士として働き始めた後、専門学校卒と大学卒では職場での役割や昇進に違いが生じることがあります。
専門学校卒の一般的なキャリアパス
- 入職後すぐに現場での実践的業務に従事
- 直接支援のスペシャリストとしてのキャリア構築
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)など関連資格の取得によるキャリアアップ
- 現場でのリーダーや主任への昇進
大学卒の一般的なキャリアパス
- 入職後、幅広い業務を経験することが多い
- 相談支援や企画立案などの業務も担当しやすい
- 管理職や経営層へのキャリアアップの道が開かれやすい
- 大学院進学による専門性の向上や研究職への転向も選択肢に
ただし、これらの違いは固定的なものではなく、個人の能力や努力、自己研鑽によって変わってくる部分が大きいことを忘れてはいけません。
仙台医療福祉専門学校で学ぶ魅力と特色

仙台医療福祉専門学校は、40年以上の歴史を持つ東北地方を代表する医療福祉系の専門学校です。社会福祉学科では、即戦力となる福祉専門職の育成に力を入れており、多くの卒業生が地域福祉の現場で活躍しています。
特に本校の特徴として、現場経験豊富な教員から実践的な授業を受けられることと、ボランティア活動や体験授業を通して福祉現場を体感できる授業が多いことが挙げられます。また、近年需要が高まっている「医療ソーシャルワーク」の基礎知識も学べる点は、就職後の活躍の幅を広げる大きな強みとなっています。
充実した学習サポートと設備
仙台医療福祉専門学校では、実践的な学びをサポートする設備が整っています。また、学生一人ひとりが安心して学業に専念できるよう、様々な支援体制を整えています。
- 実習室の充実した設備で介護技術などを実践的に学べる
- 授業では、グループワークを積極的に取り入れて、コミュニケーション力を養う
- 1年次から施設見学やボランティア活動に参加することで、現場のリアルを知り、仕事のイメージを深める
- 手話やレクリエーション、心理学など福祉現場を意識した多角的に学べるカリキュラム
- クラス担任制で教員に相談しやすい環境
- 学外実習や就職活動も教員や担当スタッフがしっかりサポート
- 社会福祉士国家試験受験を目指す卒業生向けに、卒後フォローアップ勉強会を実施
▲仙台医療福祉専門学校の社会福祉学科について詳しく知りたい方はこちら
まとめ:自分に合った選択をしよう
社会福祉士を目指す際の専門学校と大学の違いについて詳しく見てきました。最後に、ポイントをまとめておきましょう。
専門学校のメリット
- 2年間で効率的に資格取得を目指せる
- 学費の総額が大学より抑えられる
- 実践的なスキルを集中的に学べる
- 少人数制の手厚い指導が受けられる
- 就職サポートが充実している
大学のメリット
- 幅広い教養と深い専門知識が身につく
- 「大卒」の学歴が得られる
- 多様な学生生活の経験ができる
- 福祉以外の分野も学べる
- 将来のキャリアの選択肢が広がる可能性がある
どちらが「正解」というわけではなく、あなた自身の状況や希望に合わせて選ぶことが大切です。
- 時間とお金をかけてでも深く広く学びたいなら大学
- 効率よく資格を取得して早く現場で働きたいなら専門学校
特に仙台医療福祉専門学校のような実績ある専門学校なら、質の高い実践的な教育の中で、自分の進むべき方向を考えながら、福祉の多様な役割について理解を深めることができます。必要な資格を取得するだけでなく、現場に近い感覚を養い、即戦力として活躍を目指していくことが可能です。
社会福祉士としての「志」を持ち、卒業後も学び続ける姿勢があれば、どちらの道を選んでも素晴らしい福祉専門職として成長していけるでしょう。
あなたの選択が、これからの人生を豊かにする第一歩となりますように。
私たち仙台医療福祉専門学校は、福祉を志す皆さんの夢の実現を全力でサポートします。ぜひ一度、オープンキャンパスにお越しください。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。